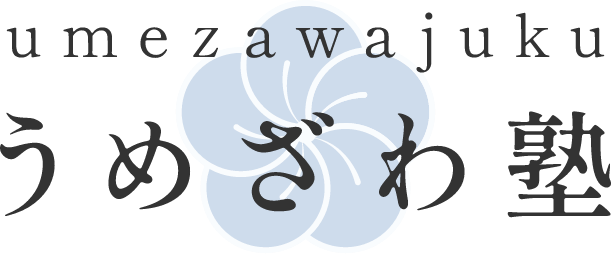四方良し(自分・塾生・保護者・社会)の前編はコチラ⇩
保護者
塾に通わせる保護者にとっての幸せってなんだろう?
成績アップ
志望校合格
もちろんそれらがキッカケであり目標です。
最終的にはそれらが得られるのは前提として、だけどそれ「だけ」あれば本当に幸せなんでしょうか。
ぶっちゃけますとサラリーマン教室長時代、「教室長」とは一見、指導者の長っぽい雰囲気ですがその実ただの営業マンであることにいささかの疑問を抱いていました。
営業マンには当然ノルマ的なモノが課せられ面談時期には「講習売りの鬼」と化することもしばしば。
社内研修では営業ロープレがさかんに行われ、指導的な要素は皆無でした。(サラッと言いましたが「皆無」ですよ?笑)
結果、それで生徒が合格するならいいんじゃね?
そんな風に言う先輩もおられましたが、だんだんと僕の中で気持ちのギャップを埋められなくなっていきました。(楽しいはずの社員旅行で酒の勢いに任せて「教室長は営業さえしてればいいのおかしくないですか!?」とブチ切れたのはいい思い出)
塾活は1年・2年、長ければ5年・6年とかかります。
その間の安心感、心の平静が得られること。
せめて、我が子が通っている塾(教室)には指導のプロがいるべきでしょう。
それでやっと、ひとまずの安心が得られる。(残念ながら「指導のプロ」とはとても呼べない人がボスであることがしばしば(泣))
いや、それであっても心配ごとは絶えないかも知れない。
子どもを持つ親として、我が子の今と将来に心がザワつく気持ちはよく分かります。
ザワつくけど、何とか抑え込んだり解消できたりすること。
つまり、指導のプロがいて、我が子を指導してくれていて、それでもなおモヤモヤする時はしっかり解消に努めてくれる。
これが大事なんじゃないかと思うんです。
毎日のように授業に立つ中で、常に自分をアップグレードさせていくのはプロとしての最低限の務めです。
そこに面談しかり、説明会しかり、ブログしかり、LINEしかり、保護者様方のザワつきを抑え込む/解消するための取り組みにも注力する。
それでやっと「通わせてよかった」と思っていただく可能性が出てくるはず。
無論、まだまだ十分ではないと思っています。
この辺りはこれからもっと拡充させねばならぬ点です。
社会
でっかいテーマですが、いきます。
教育は社会の発展に資する。
これは僕の信念です。
特に少子高齢化の昨今、合理化/効率化は必須です。
今の子どもたちが社会人になるころには、今よりもさらに緊迫しているかもしれません。
次の世代の人たちが、それでも強くたくましく生きるには教育の力が不可欠です。
AIが人の仕事をウンヌンという悲観論ではなく、今よりもっと豊かな日本で生きるために教育はもっとブーストさせていくべきです。
学歴至上主義は終わりを告げつつあります。
しかしそれをもって教育が無価値にはなり得ません。
少子化と人口減少が進み、否が応でも少数精鋭でやっていかなくてはいけない日本で、
今までみたいに何となくレールに乗っておけば終着駅にたどり着ける時代ではなくなりました。
知識・知恵は当然、身につけねばならぬもの。
それに加えて
「君はどう生きてきたんだ?」「君は何ができる人なんだ?」「君は、何者なんだ?」「君は、何をするんだ?」
こう問われる時代だからこそ、うめざわ塾は
何がやりたいの?
それで君は何をしたの?
で、これから君は何をするの?
これに答え得るだけの素養を、高校受験を経て国公立大合格を目指す中で育てていきたい。
知識・知恵を備えさせる中で
「君はどこに行きたいの? うん、なんで? この学校ってこういうところだけど、
なんでそこがいいの?」
「じゃあこうするといいと思うよ。本当にやるかどうかは君次第だけどね。やらないせいで悪い結果が出ても全部自分で責任取りな」
こういうスタンスで塾生と接していきます。
冷たく見えるかも知れませんが、優しく後押し、べったりフルサポートの方が酷だと思います。
教育とは名ばかりの、依存しないと自分のことすらままならない人間を作るようなことをしてはいけない。
加えて民主主義国家として、国の行き先を決めるのは国民(有権者)です。
最終的な意思決定を下すのが国民である以上、日本で(または世界で)何が起こっているのかが理解できる(少なくとも、しようと思えばできる)水準に子どもたちを教育しなければ健全な民主主義は機能しません。
こんなちっぽけな一地方の学習塾が偉そうに語っていますが、うめざわ塾がよりよい社会作りに1ミリでも寄与できたなら僕は幸せです。