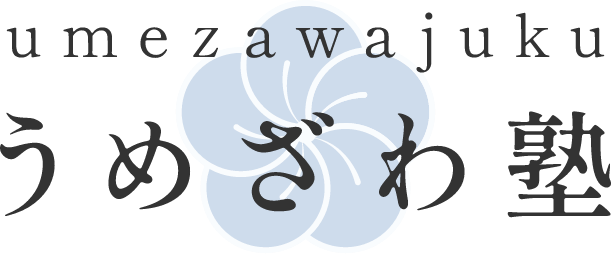模試の「A」とか「C」とかの判定が
オレが合格する可能性
ウチの子が受かる確率
と誤解されがちなのでちゃんと説明します。
模試の判定はだいたい
S:80%超
A:80%
B:60%
C:40%
D:20%
E:20%未満
とされますが、その「〇〇%」は
キミの偏差値だったら去年は〇〇%の人が受かってたヨ
の意味です。
例を挙げます。
総合模試ベースだと二水は「偏差値57」でB判定をもらえます。
これは「偏差値57の人は去年、60%の人が受かってたヨ」になります。
これが「オレの合格可能性」とどう違うのか?
例:合格判定が「B=60%」だった場合
①オレは10回受けたら6回受かるんだな → ✕
去年はオレと同じ偏差値の人で60%が受かってたのか → 〇
②ウチの子は5回に2回落ちるんだわ → ✕
去年はウチの子と同じ実力だった人の40%がダメだったのね → 〇
仮に今回C判定だったとしても、去年は同じCだった人たちの40%は受かってますし、
たとえA判定だったとしても、同じAの中で20%は落ちました。
なんとなく「A=安心」「B=セーフ」「C=ダメ」「D=ダメ」くらいに思っている人も多いですが、この機会に正しい判定の意味を掴んでおきましょう。
極論、Dでも20%は受かってたってことです。
※Eはさすがに、受験回避しましょう。
この60%やら40%やら20%やらに入るためにはどうしたらいいのか?
当日まで頑張り抜く
当日に最高のパフォーマンスを出す
これしかありません。
直近で言うと第七回模試、つまり1月12日の時点で「B」だったのなら、
同じBだった子たちに本番で勝つよう、追い抜くよう、精進し続けるのです。
そして本番で自分の力をすべて出し切れるよう準備をするのです。
これを怠れば、甘えれば、残念だった40%に入ってしまうということです。
受験が近付くと、模試の判定で一喜一憂する日々になりがちです。
そうなると、受験の沼にハマります。(そういうときに塾産業の魔の手が忍び寄ります)
模試の判定の意味をキチンと捉え直して、いざ志望校へ向けて、今まで以上の努力を。
※実際の意味での合格可能性が気になる方は、信頼できる塾の先生に聞きましょう。
数値化はできないでしょうが(問題も受験者数も受験者個々の実力も不明なのに数値化できようはずもない)、
「ぶっちゃけ、このままでいいのか、変えた方がいいのか」は答えてくれると思います。
模試の数字に振り回されず、「何を積み上げるか」を考えることが一番大切です。
努力の扱い方については、⇩コチラ⇩にも書いています。
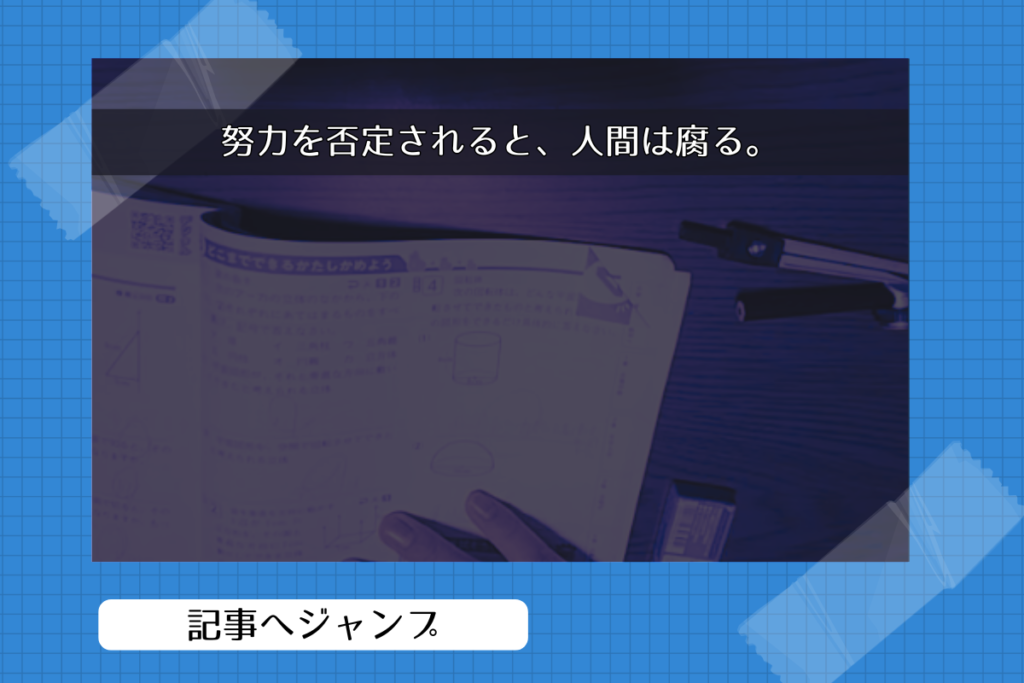
====⇩うめざわの最新記事⇩====